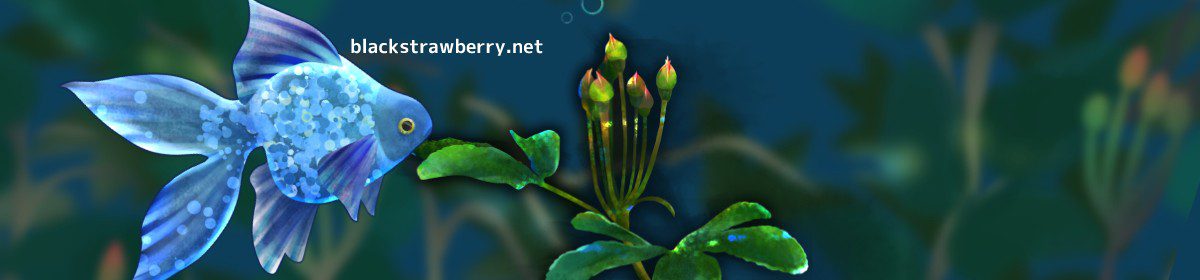唐突にいま読んでる3巻の感想を書く。3巻というか、読み返してたら言いたいことができたという理由で書きますよ。
数少ない好きな少女まんがということで(というかどれもジャンルにしたらそんなに無いのかも……少女漫画をあんまり読めていない気がするので)
年に1回ぐらいは読み返しているのです。
私が読む少女漫画のほうでは新しい作品かもしれない、といいつつ、平成初期のマンガです。
有名作品なんでネタバレとか気にせず、あとネタバレとかで大枠がバレたところでこの作品の良しあしにはあんまり関係ないですよ。
衝撃の展開!という内容ではなく……と言うとそれもまた違う気がする、ひとつひとつのエピソードは「へえ!」「そう来たか!」という感じでわくわくするんですけど、どんでん返しとか予想を裏切る展開!とかそういうバレてるとつまんなくなっちゃうネタじゃなくて、ディテールを楽しむような感じ?
1巻の表紙からイチャイチャしてるじゃないですか。でも正直1巻のうちは全然イチャイチャしてないですよ。どっちかというと、男の子キャラ・入江くんはひどい男で、冷血で、あんまり人の心とかを考えるタイプではなく、冷めていて「どーでもいい」「頭の悪い人間嫌いなんで」みたいな感じで何にも興味がないわけですよ。とにかく感情が平坦で動かないタイプの人間なわけです。
逆に主人公の琴子は、補って余りある動きの多いキャラで、行動的で、好きなものにまっしぐらで、「やってみたい」って感じでどんどんやってみては失敗したりしている。凹んだりもするけどやっぱり挑戦するタイプのキャラ。
全編をとおして、この漫画の中では「入江くんが琴子に振り回されるうちに、感情を出したり、困ったり、対処したりしてどんどん人間らしくなっていく」という話なんですよね。琴子の成長……もあるけど、基本的には琴子がいかに入江くんをいい男に成長させていくかという話なわけですよ!!
すれちがい、勘違いや思い込みでうまくいかないこともあるけれど、そんなに長くズレっぱなしにならない(ここ重要、読んでて不安になっちゃうもんね)し、読者目線ではもうわかっちゃうんだよねこのカップルが「間違いない」ことがね。
物語としてはストレートに語られているようで、細かい技法には毎回気づかされてドキッとしてしまう。さりげないせりふ回しで、セリフの裏に隠れた本当の気持ちみたいなのが表現されていて、気づかなくてももちろん大丈夫だし気づくと「ああ、もうここでその気持ちが出てたんだ」とじーーんとしてしまう。
入江くんはもうかなり初期の段階で、琴子のことが好きでほかのやつになんか取られたくないって思ってるっぽいんだけど、本人も気づいてないんだよね。読者がもし入江くんに話しかけられるとしたら「入江くん、それはもう琴子のことが好きなんだよ」と言ってしまいたい気持ちにすらなるね!早く気づけ!!って思っちゃう。そこがいい。
気に入ってるのは、最初苗字で「相原」って呼んでたのが、ある時を境に「琴子」って呼ぶようになって、その後もう相原に戻らずずっと「琴子」なんですけど、その切り替えがほんとさりげなくて自然で好き。
他の男(ライバルのようで全然ライバルになれていない)・金ちゃんが、普段から仲良しだという立場から「琴子」って呼び捨てにしているのに対して煽る目的で「琴子にね」って言って見せた後は、ずっともう琴子。
呼び捨てイベントが作られてもいいぐらいなわけですが(実際ほかのまんがとかだと、呼び捨てとか名前で呼ばれる瞬間ってので1エピソード描いたりするよね)そういうこともなくさらっと。ああーーいい。
入江くんは「はっきり言うけど嘘はつかない」キャラなのですが、たびたび琴子にせめられて「なんか反応しなくちゃいけない」シーンになることがあるのですが、そのたび上手に?嘘にならないようにはぐらかしてるんですよね。そこがいい。
「あたしとまた住むのがイヤならイヤって はっきりいえばいーじゃない」
「意地悪? そうだよ おまえ見てるとイライラしてくるんだよ」
(文庫版3巻78p)
「住むのがいやならはっきり言え」という琴子の煽りに乗らずに
「意地悪がイヤだったら目の届かない場所にいけよ」とかわすわけですよ。
琴子としては「ガーン!ひどいこといわれた」という場面になるんですが、読者目線だと「琴子!入江くん一緒にすむのがイヤだって言わないよ!!」となるわけ……ですよ。こういう細かいずらしのテクニックを使って入江くんはうまいこと
「自分の気持ちをはっきり言わない、でも嘘はついてない」
という状態に常に持っていくわけですよ。
この会話劇はすごいと思うのです……もしかすると多田かおるさんはそれを計算抜きでやってのけてるかもしれない。計算しててももちろんすごいわけですけど。
この調子で、今回の読み返していくつ「会話の妙」に気づくことができるだろうか。いや~まだまだ発見があるなあ……