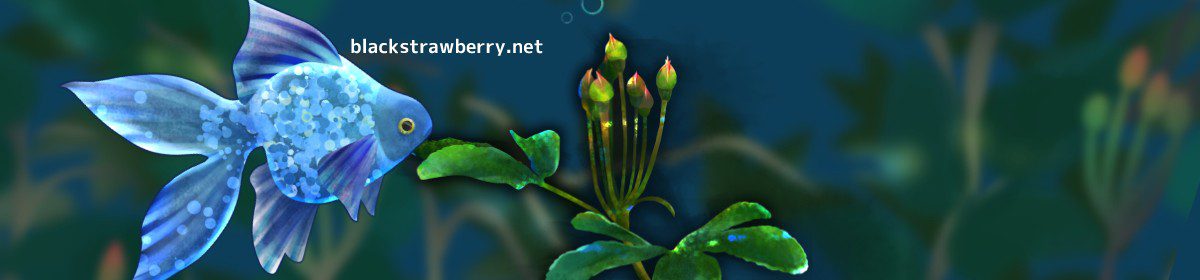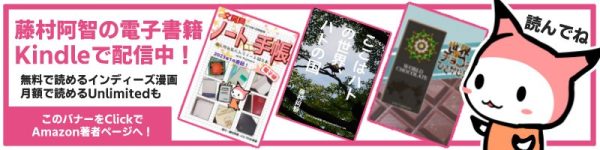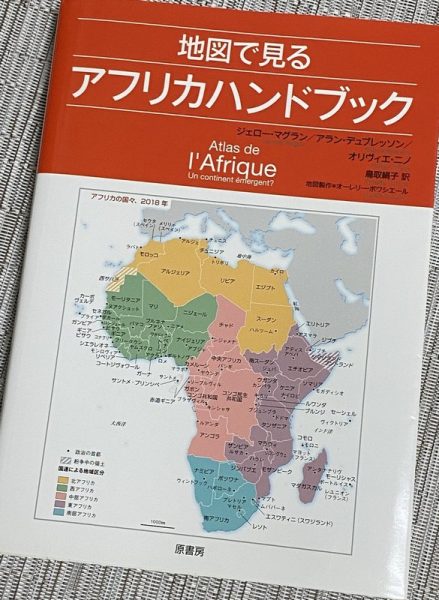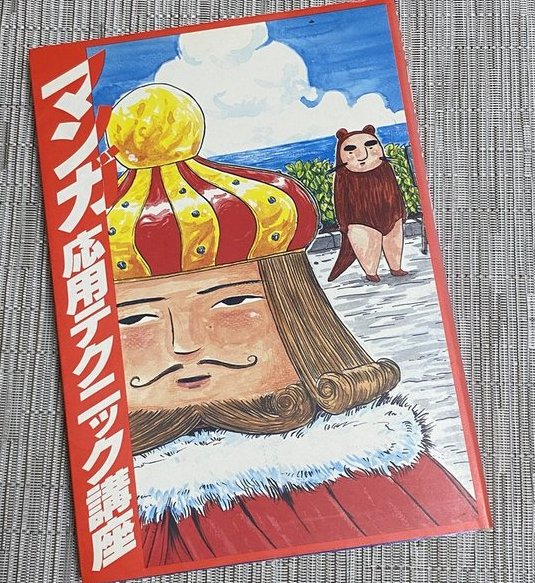その他の記事も 2024年本棚の本の紹介 から読めます。
生還
羽根田治 ヤマケイ文庫/山と渓谷社
ヤマケイ文庫 ドキュメント 生還―山岳遭難からの救出 | 山と溪谷社
https://www.yamakei.co.jp/products/2812120101%20.html
電子書籍で持っている本なので写真は無し。
私は山岳遭難の本をいろいろ読んでいる。最初に読んだものはどれだったか……「生還」は数冊目だったと思うのだが、では最初は何だったか思い出せない。同じヤマケイ文庫で羽根田治さんの「道迷い遭難」か「滑落遭難」か?
本を読み始める前は、「ヤマレコ」のようなサイトに投稿される体験談で遭難の事案を見ていた。
ヤマレコ-登山やハイキング、クライミングなどの記録を共有できる、登山の総合コミュニティサイト
https://www.yamareco.com/
人はどういう風に遭難してしまい、どのように救助されるのだろう。そんな興味から遭難の本を読み漁った。いくつか読んでいるうちに、「ひとくちに遭難の本と言っても、遭難や山・登山に対しての考え方が筆者によってだいぶ違うんだな」ということがわかってきた。ひとによってはだいぶそこが「合わない」と感じる著者もいる。
「生還」の著者の羽根田治さんの本は好きでいろいろ持っている。2024年にでた「生還2」も読みたいと思いつつまだ購入していない。
文章の本縛りで「うちの本棚にいちばんたくさん本がある著者はだれだ?」と考えると、羽根田治さんになるのである。
つまり、山に対する考え方、登山をするということ、遭難ひとつひとつの取り上げ方、遭難者に対する取材したジャーナリストとしての視点がいちばん「いいな」とわたしが思う著者だということだ。
「生還」を選んだのは、この本に掲載されている遭難者はみな生きて帰ってくるからである。遭難して亡くなる人も多く、事件の検証としても亡くなったあとに状況から推測することになるのだが、「生還」なら本人への取材も可能だ。遭難してしまった本人の言葉が知れるのもいいことだと思う。基本的にはみな「山はこりごり」などと言わず、また山に登っているようなのもちょっといいなと思う。
ドキュメント生還2 長期遭難からの脱出 | 山と溪谷社
https://www.yamakei.co.jp/products/2823340460.html
その他の記事も 2024年本棚の本の紹介 から読めます。
—【広告】—
【藤村阿智の電子書籍】
★AmazonKindle ★BOOK☆WALKER ★BOOTH ★BCCKS
—【広告ここまで】—